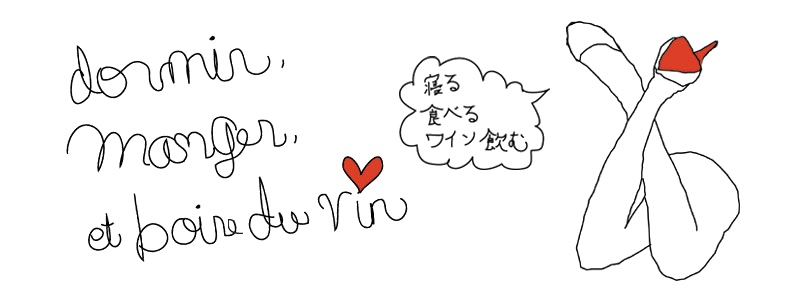わたしの入居と入れ替わりで日本へ帰国した友人がアパルトマンの鍵と一緒に、電話番号とKyokoと書かれたメモをくれた。
「ここに電話してわたしの紹介ですって言えば、大丈夫。とにかく、フランス人に髪の毛を切ってもらうのは止めといた方がいいよ。」 その電話番号が京子さんの携帯番号だった。
京子さんと初めて会った日に、それまでボブのストレートヘアだったわたしは、彼女に強いパーマをかけてもらった。なぜだかわからないがParisに住み始めてから無性に強いパーマのかかったスタイルにしたくなった、というのを京子さんに言うと、彼女は笑った。日本人の若い女性はほとんどが栗色に髪を染めて パーマをかけたとしてもゆるくふんわりとした、いわば欧米人のようなヘアスタイルを希望するそうで、そうかと思えばParisに長く住む日本人女性はほとんどが黒髪のストレートロングヘア志向の人が多いらしく、京子さんはそのどちらでもない趣味のわたしを面白がり、「久しぶりにこんな強いパーマをかけられる~!」なんて楽しんでくれた。その日から京子さんとは時々ご飯を食べに行ったりお茶をしたりする仲になった。
ところでParisに長く住むと日本人はなぜかみんな「Parisで一番美味しいPhoの店」のアドレスをおのおの持つようになるようなのだ。色んな人が、あそこがParisで一番美味しいPhoを出すお店だよ、と言うのを聞いた。
わたしはというと、結局帰国の日まで、「自分の一番美味しいPhoの店」を持つことはできなかった。どこのを食べても美味しいし、だけどまあまあ似たような味に感じていた。わたしが思うにおそらく「Parisで一番美味しいPhoの店」のアドレスを持つということは、Parisに住む年月に深くかかわっている。それは醤油味に似た味わいを欲し、自分の欲求を納得させるほどのアドレスを見つけることへの切実な探求あってこそなのだ。1年やそこらでわたしはそんな切実にアジア味を恋しくなることはなかった。食べれたら食べるでいい、食べられないなら別にそれはそれで構わなかった。
というわけで、その日わたしは京子さんに誘われて彼女の「Parisで一番美味しいPhoの店」に行くことになった。彼女のPhoの店は、Parisでも一、二を争うくらい有名なPhoのお店のすぐ隣にあった。その有名なPhoの店はいつ通りがかっても、店の前に長い行列ができている。彼女曰く、その有名な店のPhoはツーリスト向けなのだそう。とはいえ、以前彼女もその”ツーリスト向け”のPho目当てで来た時、その長い行列を見てあきらめ隣の店に入ったところ、このParisで一番美味しいPhoに出会ったのだそうだ。
目の前に出てきたのは真っ赤なPhoだった。唐辛子がふんだんに入った、Phoにしてはこってりとした濃厚なスープで、ふたりしてふうふう汗をかきながら食べた。スタンダードなPhoではないが、なるほどクセになるような、何ヶ月かに1回くらい無償に食べたくなるような、そんな味だった。
フランスには、旧植民地であったベトナムから移住してきたベトナム人が多く暮らしている。特にこのカルチエは、フランスだと思えないほどベトナム料理屋や中華料理屋がひしめくように並び、ベトナム人や中国人がたくさん住んでいる。看板の派手な色の組み合わせや、聞こえてくる中国語かベトナム語かだかの喧騒はまたたくまにアジアの街にトリップしたような気にさせる。そして歩いているとなんだか不思議と元気になるのだ。そんな時、やっぱり自分はアジア人なんだななんて感じる。
わたしは、彼らと一緒に居るのが楽な時もあれば、フランス人の友人と居る方がしっくりくる時もあった。
そしてわたしはそれぞれの日本人たちと関わり合うなかで、その人たちがふわりと身にまとっている、Parisの街の独特のオーラを感じをうけるようになった。たまに日本から友人たちが旅行で来た時、その友人たちの日本から持ってきたオーラは、Parisに住んでいる日本人たちのそれとは違いすぎて、どちらがいいとか悪いとかそういうのではなく、ただただその違いを感じてはわたしはなぜか自分だけがどちらでもなく、ひとり漂っているような不思議な感覚になっていた。
そういう感覚が強くなる時、こんなアジアのどこかのような、それでいてアジアのどこにもないような場所に来ると、なぜだかほっとするのだ。
ここもまぎれもないParisの一角。